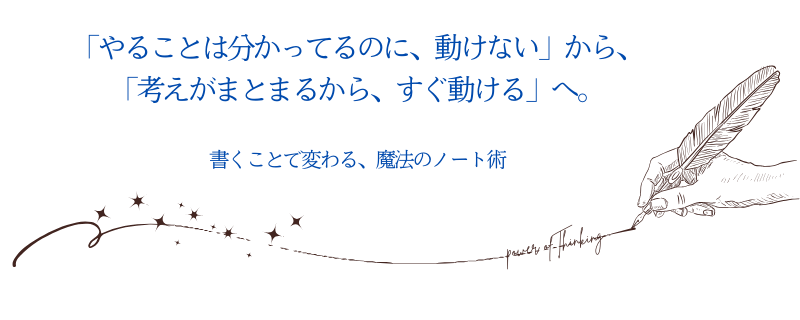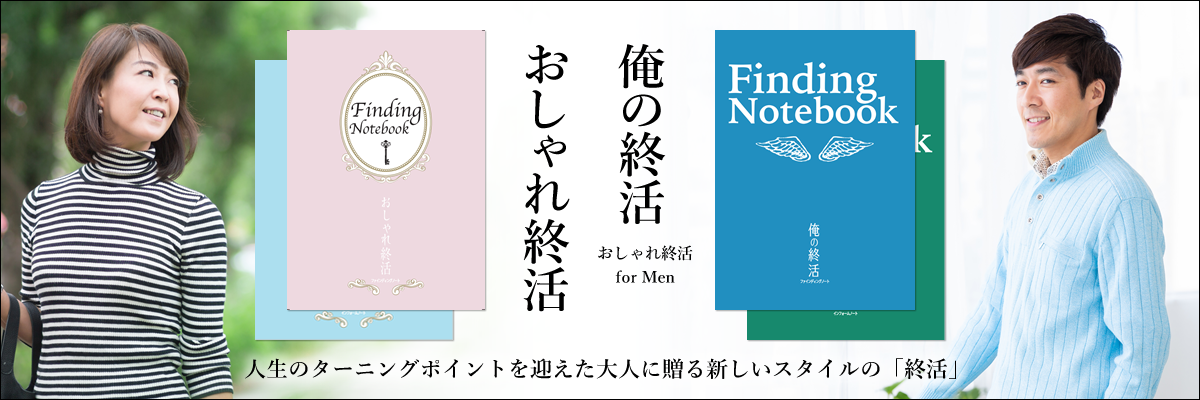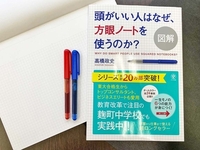- ホーム
- 人生の器の整え方・100日ブログチャレンジ2023
- キッチンの片づけでプロが実践するポイント3つ!
キッチンの片づけでプロが実践するポイント3つ!

こんにちは、
今日のコラムは
「家じゅうを片づけたい!」と思ったときの考え方。
じゃあ、どうすればいいの?
というと…
オススメは、場所ごとに区切って、片づけていくこと。
今日は、
その中でもキッチンの片づけで、私たち「片づけのプロ」が実践しているポイントを
3つ、お伝えします!キッチンは、場所の目的・役割がハッキリしていて、
「この場所は、何があればいいのか?」を考えやすいので、収納するアイテムも決めやすい場所です。
キッチンは、料理を作る場所ですね。
料理は、私たちの身体と健康をつくりますから、キッチンの片づけは健康づくりにつながっている!と思います。
片づけと言うと「捨てなきゃ!」って思ってしまう方も多いようですが、
キッチンは捨てる量が少なくても、収納場所・しまい方によって、グーンと使い勝手が快適になります。
お客様からも「すごく使いやすくなった!」と喜んでいただいています。
片づけのプロが実践する、キッチンの片づけポイント3つ
①「仲間」ごとにグループをつくる
キッチンでは、細かいモノや様々な食材が混在しています。
まずはすべて出して、「仲間」ごとに分けましょう。
例えば、昆布と鰹節は「出汁をとる・乾物」という一つの仲間にできます。
「出汁をとる」点に着目すると、粉末のだしやコンソメなども、同じ仲間になりますね。
お茶、紅茶、コーヒーなども、大きなグループで「仲間」となります。
鍋やフライパンは、焼く・煮込むなど調理をする仲間、菜箸やレードルなどは調理器具、
メジャースプーンやピーラーなどはキッチンツールの中では「下準備をする」仲間です。
食器や嗜好品は、シーンごとに分けるのもおすすめです。
毎日使う家族の食器と、お客様用の食器は、別の仲間…ということです。
こうやって見ていくと、様々なグループで、キッチンが出来上がっていることが分りますね。
仲間ごとにグループにしたものは、仕切りやカゴを使って、仕分けした状態で収納場所をつくります。
食材に関しては、使い切れるようにしていきたいですね。
②「適正量」に収める
仲間ごとにグループをつくると、そのグループの総量=全部でどれくらいの量を持っているのか、ハッキリします。
そうすることで、「多すぎる」「足りない」が目で見てわかります。
多い・少ない、というのは、それぞれのご家庭でのライフスタイルによります。
例えば、自宅では日本茶をよく飲む・コーヒーは飲まない方なら、コーヒーのグループは不要で、
よく飲む日本茶には量(ストックなど)が必要だということが分ります。種類を充実させるのもいいですね。
乾物や、調味料は、1カ月でどれくらいの量を使っているのかをチェックしてみると、ご自分でペースが図れます。
多すぎる食材はしばらく購入を待って、うまく使い切るように習慣づけましょう。です。
食器類は、ご家族の人数と照らし合わせて考えましょう。
特に「○○にしか使わない」といった専用食器は、数が多すぎないか、チェックしていただきたいものです。
ちょうどよい数量のことを「適正量」と言います。
実際に使っているかどうか、食器棚やパントリーといって収納スペースにゆとりをもっておさまる量か、
に気を付けて決めるといいですね。
③「しまい方」を考える
「あまり使わないモノ」を「よく使うモノ」と一緒に収納していると、
目当てのモノを見つけるのに時間と手間がかかります。
仲間でグループに分けて、それぞれの適正な量を決めたら、
「よく使うモノほど手が届きやすいところ」に収納場所を決めていきます。
この時「よく使うモノはサッと取り出せる」のが大事です。
お子様が料理のお手伝いをされるようになったお客様のお宅では、
それまでは箱にしまっていた「予備のキッチンツール」を、
ツールスタンドで立てて収納するように替えました。
「たったそれだけ?」と思われるかもしれませんが「とってもラクチンになりました!」と喜んでいただきました。
以前は、
<1箱を取り出す→2箱のフタを開ける→3目当てのアイテムを取り出す→4フタを閉める→5箱をしまう>
と、手順が5つあったのが、
<1手を伸ばして、目当てのアイテムを引き抜く>だけ、
というたった1つだけの手順に変わったのですから、ラクチンなわけです。
毎日使うモノ、よく使うモノを厳選して、手が届きやすい場所にしまうことから始めましょう。
逆に、いつもは使わないアイテムは、箱に入れる・袋に入れるなどして、食器棚などの収納スペースに収めましょう。
よく使うモノと、たまにしか使わないモノは、別の場所にしまうことで、探し物の時間もグッと減りますね。