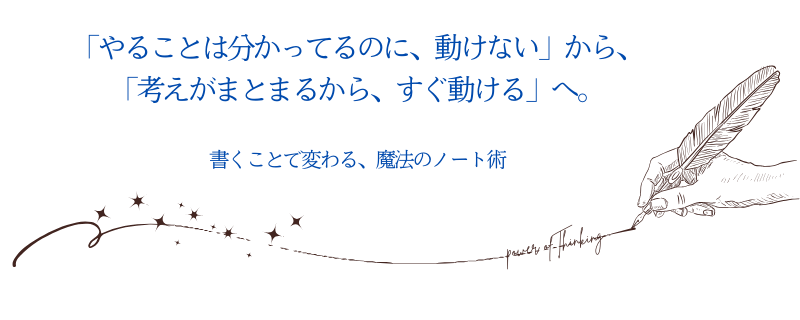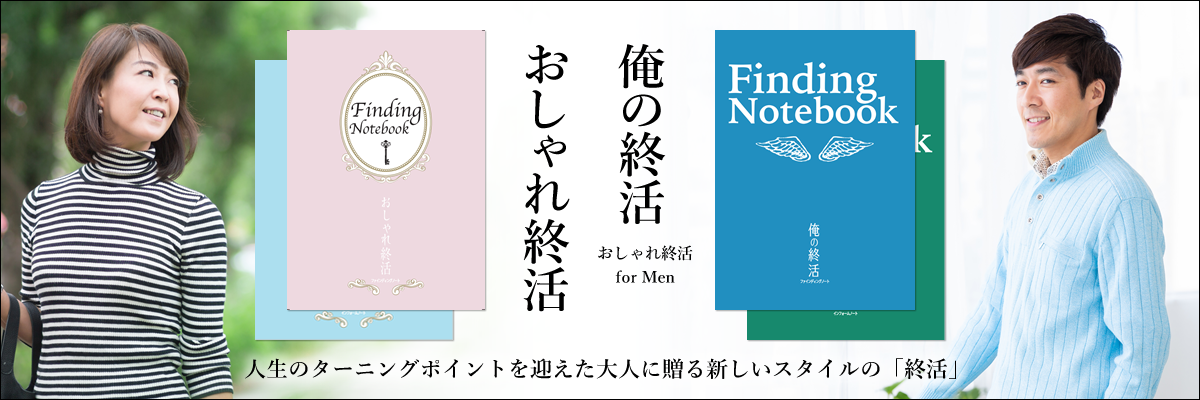- ホーム
- 片づけ心理学コラム&ブログ
- 家庭の薬は3種類!ゴチャつき解消の置き場所・収納ポイント
家庭の薬は3種類!ゴチャつき解消の置き場所・収納ポイント
「薬」というモノは、使わないようでいて、使うモノです。
秋から冬は風邪、夏は冷房などの冷えからくる腹痛、春は花粉症…
テレビのCMも、季節ごとに移り変わっていきますね。
そんな日常の薬、どこにしまっておられますか?
お客様のお宅で、多く見かけるのは、こんな光景です。
・救急箱に入れてある
・空き缶に詰め込んである
・出しっぱなし(ダイニングテーブルの近くなど…)
片づけのプロたちの場合は、こんな言葉が出てきました。
・全ての薬を救急箱にまとめてリビングに収納
・引き出しに集合させている
・よく使うモノだけは、表に出している
今回は、
細かいけれど「チリも積もれば山となる」…まとまりにくくてゴチャゴチャしてしまう、お薬の種類と収納ポイントについて。
「薬」は、「飲む頻度」で3種類に分かれます
 ふだん、まとめて「薬」と私たちが呼んでいるものは、3つの種類に大きく分けることができます。
ふだん、まとめて「薬」と私たちが呼んでいるものは、3つの種類に大きく分けることができます。
①家庭の常備薬
②常飲している薬
③一時的に飲む薬
それぞれ、使用頻度(どれくらい使うか)が違いますので、収納の方法も変わってきます。
では、種類ごとに解説していきます!
どれくらい使うか=頻度ごとに、収納・定位置のポイントが違います
 ①家庭の常備薬
①家庭の常備薬
消毒薬、絆創膏、傷用の軟膏、引き初めの風邪薬、痛み止めなど。
いざという時には、サッと取り出して使いたいものですが、普段は使用しないものです。
これらをまとめて収納するのが「救急箱」の役目。
救急箱をわざわざ買うほどでもない、という方は、リビングの引き出しなどに「救急用の薬」を入れる場所を決めましょう。
箱や引き出しには、なるべく立てて収納し、上から見た時にわかるように工夫しましょう。
※引き出しの写真は、スタッフのお宅の薬を入れている引き出し。②常飲している薬
持病などのために、病院で処方された特定のもの。
①と違い、毎日飲む薬ですね。
飲み忘れないようにしたいものですから、目につきやすく、手が届きやすい場所に収納します。救急箱には入れません。
例えば、ペンスタンドや器など、置く場所を決めておくのがよいでしょう。
小さな紙袋に入れた薬を、冷蔵庫につけたマグネットフックにひっかけておくのも飲み忘れ防止に効果的です。
「その場所に手を伸ばせば、すぐに飲める」状態になるのがベストです。
一度に処方される量が多い場合は、小分けにして「当面飲む分量」と「ストック」に分けると管理しやすくなります。
③一時的に飲む薬
風邪など、一時的な病気の症状を治療するために、処方された薬。
③が家にある時は「今、飲む必要がある薬」ですから、②と同じく、目につきやすく、手が届きやすい場所に収納します。
期間限定の置き場所ですね。
しっかり飲んで、症状が治まった後、薬が余っている場合は誤飲を防ぐためにも、処分されることをおすすめします。
収納を考える時のポイントは、「よく使うモノほど、手が届きやすいところに」です。
「薬を飲む」という行為は、細かいからこそ、使用頻度に合った収納を考えて見直すと、毎日の暮らしがスムーズになりますよ。