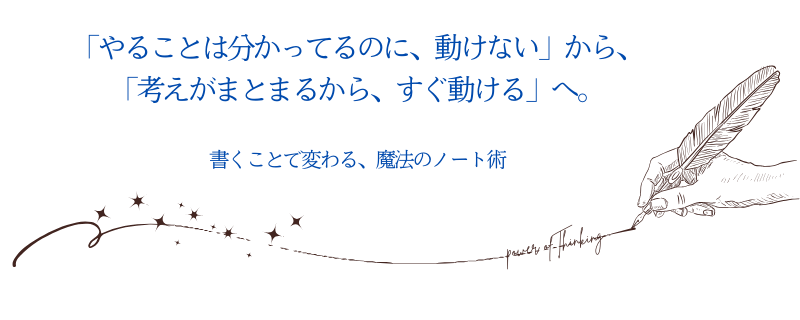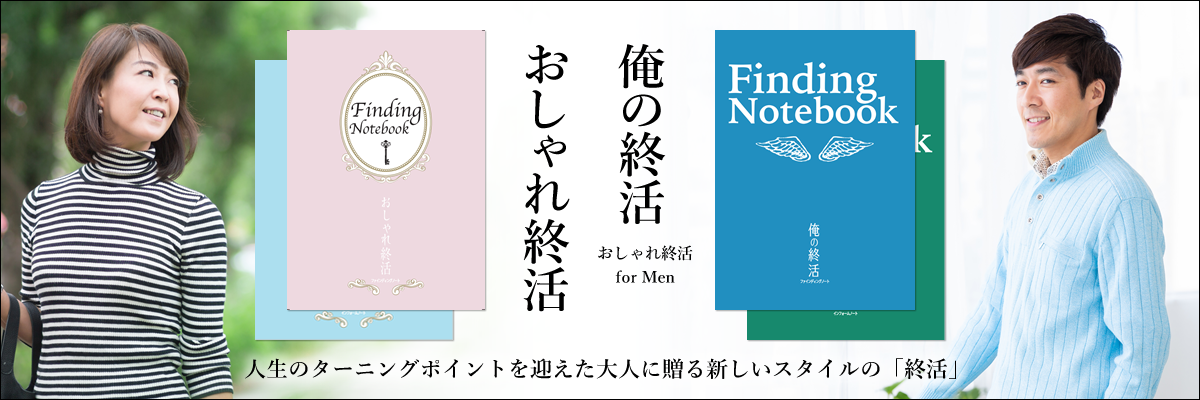- ホーム
- 片づけ心理学コラム&ブログ
- 悩む人が多い「押入れの片づけ」5つの手順を、実例で解説
悩む人が多い「押入れの片づけ」5つの手順を、実例で解説

「押入れの片付け」については、多くの方がお悩みですね。
片づけサービスでも、ご相談が多い場所です。
今回は、
実際に私たち「片付けのプロ」が片づけを行う時の手順を、
お客様のお宅で行った、サービスの写真と共に、ご紹介します!
※本文中の写真は、お客様にご了承いただいた上で掲載しています。
1 現状、悩み、どうしたいのかご要望を確認
今回片づけるのは、寝室にある押入れです。
部屋の角にあり「開き扉が全開しない」のが現状です。
上段には布団が詰め込まれている状態、下段には大きなダンボール箱が入っています。
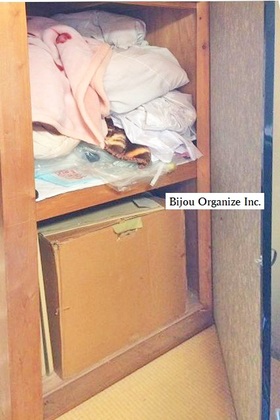
お客様のお悩みは…
・お布団がバラバラに入っていて使いにくい
・下の段や天袋をもっと使いこなしたい
2 全て出して「何が入っているのか」を点検!
もっと上手に使いたい、とお悩みだった下段の大きなダンボール箱には、
「端午の節句人形セット」が入っていました。
季節には丁寧に飾られ、収納もきちんとされています。
問題は、収納されている場所ですね。
この扉は全開しないため、
大きく重い節句人形の箱は、出し入れがとても大変な状況にありました。
3 どれくらい使うモノか=頻度を考える
節句人形の使用頻度は、1年に1回です。
(年に一回、出す・飾る・しまう行為が行われる、ということ)
押入れの使い勝手を考えると、
下の段には、もっと日常で使用するモノを収納したいところです。
そこで、天袋へ移動することにしました。
天袋には…
・急に入院しなければならなくなった時に、
必要なモノをまとめた「緊急入院バッグ」が入っていました。
これは、お客様の健康状態に関わることです。
緊急の時には、サッと取り出したいわけですから、出し入れの際に、
脚立や踏み台が必要になる場所に収納するのはNG。移動することにしました。
4 高い収納スペースは手が届きにくい!モノの大きさ・重さを調整する
節句人形の大きな箱は、サイズから考えても、
大きなダンボール箱のまま、天袋に収納することは困難です。
また、重いモノを目線よりも上の位置に収納してしまうと、
取り出すときに脚立や踏み台の上で、
不安定に態勢になり、危険です。
そこで、
モノの大きさ・重さを調整する必要があります。
重い箱から、小分けの箱を取り出して、
「小さな箱」で、取り出しやすいようにひとつずつ、収めていきます。

5 手が届きやすい上段・下段には、よく使うモノを収納
大きなスペースが空いた下段には、
中段いっぱいに詰めこまれていた布団を収納することにします。
布団も、分類します。
種類、使う人、季節などを考えると分けやすいですね。
下段には、重い敷き布団、かさばる羽毛布団を。
中段には、ブランケット、毛布、薄手の掛布など。
中段の手前には、緊急入院要のバッグを納めました。
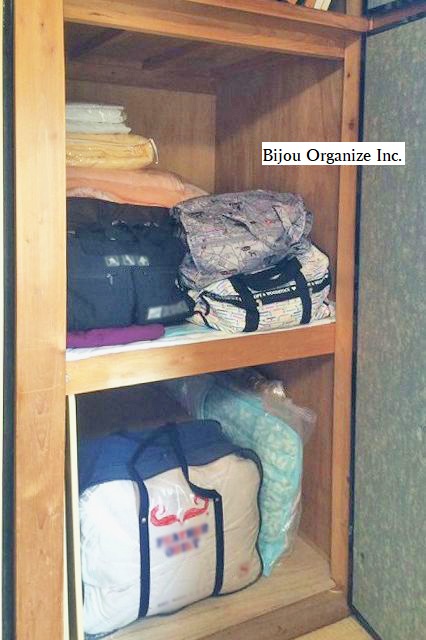
いったん、完成です!
※さらに、出し入れしやすくするために、
この場所には、後日、押入れ棚を設置しました。
収納スペースの片づけポイント3つ
今回、押入れに入っていたモノの分量は、
節句人形をまとめていた大きなダンボール箱を処分した以外、それほど減らしてはいません。
「何をどれくらい使うのか」
頻度に合わせて、収納の位置をつくることで、
どの位置も、どこに何があるかがわかり、使い勝手が良くなりました!
押入れに限らず、収納スペースを片づける時には、
・自分がよく使うモノ、使うシーンを考える
・よく使うモノを手が届きやすい位置に収納する
・収納するモノが決まってから、収納用品を買う
3つのポイントで考えてくださいね!